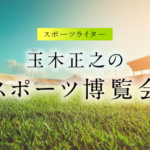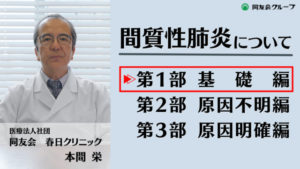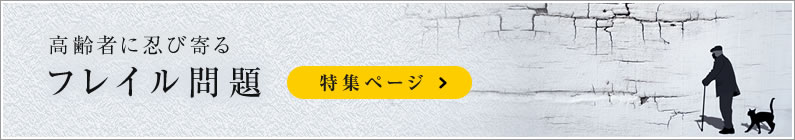コラム

玉木正之のスポーツ博覧会
2025年11月27日
敵はテクノロジーにあり!?

アメリカ大リーグは来シーズンから、投手の投球の「ボール/ストライク」の判定に、いわゆる「ロボット審判」の活用を決めた。正式には「ボール/ストライク自動判定チャレンジ制度」というもので、まず球審が「ボール/ストライク」の判定を行い、その判定に、打者か投手か捕手が不満だった場合、ヘルメットを手で触るという行為で「チャレンジ」を表明する。
すると、ホームプレートを囲んだ6台のカメラが、あらかじめ計測した打者の身長とホームプレートの位置からストライクゾーンを確定し、投球がそのゾーンを通ったか否かを判定。それを画像でスコアボードに映し出し、ボールかストライクかを最終的に決定する、というものだ。
チャレンジの権利は、1試合に付き攻撃側(打者)と守備側(投手と捕手)に各2回与えられ、主張が通れば権利の回数は減らないが、主張に失敗すれば権利は減る。ただし延長戦になった場合、権利がゼロになったチームには、各回ごとに新たに1回の権利が与えられる、というものだ。
韓国のプロ野球では、昨年からロボット審判の判定が、球審の耳に付けられたイヤホンに伝えられ、その判定を最終決定にしている。が、大リーグでは、その方式もマイナーリーグで試した上で、人間的な判定の要素を残したいという意図から、ロボット審判の判定は、チャレンジの後に使うことにしたという。
テニスやバドミントンやバレーボールの「イン/アウト」、タッチネットやオーバーネットなどの判定にも「チャレンジ」にカメラとコンピューターが用いられ、サッカーのゴールもボールの中のICチップが決める現在、アスリートの「敵」は、人間ではなく科学技術(テクノロジー)になったようだ。
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。