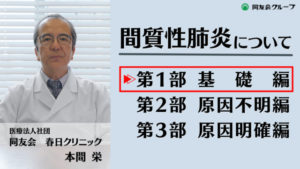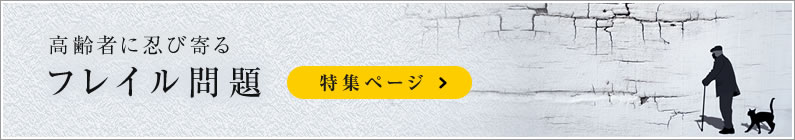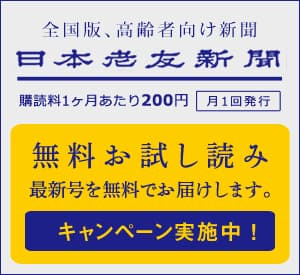コラム
浮世〈現実の世を愉しむ姿勢〉

(本稿は老友新聞本紙2019年11月号に掲載されたものを一部修正したものです)
「浮世」と聞くと皆様は何を連想されるでしょう。「浮世の義理」「浮世離れ」という言葉や「浮世絵」がまず頭に浮ぶと思います。
浮世絵といえば、菱川師宣、鈴木春信、喜多川歌麿の美人画や東洲斎写楽の役者絵、葛飾北斎の『富嶽三十六景』、歌川広重の『東海道五十三次』が代表的なところでしょうか。浮世絵の画題は、庶民に喜ばれる風俗、風景、役者などを取り上げ、肉筆画と木版画があります。中でも単色摺りから錦絵に発展した版画は、フランスの印象派に強い影響を与え、浮世絵は日本が世界に誇る文化遺産なのです。
「浮世絵」の「浮世」を辞書で調べると、辛くはかない世の中、変わりやすい世間と出ていますが、今回はその歴史と意味を探ってみましょう。
大阪夏の陣の後、やっと戦国乱世に終止符が打たれて平和の世となり、武器を納めて用いないという元和偃武となって、将軍のお膝元の江戸は世界最大百万都市に発展しました。庶民芸術と言うべき浮世絵はこの頃から作られ、ヨーロッパの印象派画壇にも大きな影響を与えたのです。浮世絵の「浮世」とは、この元和偃武により平和となった現世を思う存分楽しむ姿勢を示し、中世の無常観の「憂き世」から決別して、現世を楽土とする考え方の「浮き世」へと変じたところから起きた思想です。
慶長末期(1615年頃)は当時の流行歌に記されている「うき世」は、厭世観に根ざされた享楽思想の意味で、遊楽生活や恋愛事を表していました。しかし、明暦の大火(1657年)で江戸の約6割が焼損すると、この災害が契機となり江戸再計画が進み市中に町人の活躍の場が広がり、厭世観を一気に吹き飛ばす「浮世」の思想が確立したのです。
浅井了意という人が寛文5年(1665年)に書いた『浮世物語』に、「世に住めば、いろいろ良いことも悪いことも、見たり聞いたりすることみなおもしろく、先のことなどは全く予知出来るものではないから、どうということもない将来については、へちまの皮ほど気にせずあれこれ気にかけるのは健康に悪いから、その場その場で適当にうっちゃって、月・雪・花(桜)紅葉など四季の美しいものを眺め、歌を歌い酒を飲み、思いっきり浮かれて楽しんで、金がなくても苦にせず、くよくよと考えないで、水に流れる瓢箪のように浮き沈みのない心意気この世を生きる。これを浮世というのである」と書いています。いつどんな災害に見舞われるか明日も不安な現代だからこそ、この文章は心に響きよくぞ書いてくれました。それでいいのだ! 心の底から思います。
浮世絵は、この現実を背景に、当世の風俗を描いたところから始まり、浮世絵という言葉は、天和元年(1671年)に刊行された俳書の中に初めて見られます。この頃は、浮世絵の成立に大きな役割を果たした菱川師宣の作画期にあたるので、「浮世」思想による浮世絵が創始されたものと考えられています。
(本稿は老友新聞本紙2019年11月号に掲載されたものを一部修正したものです)
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。