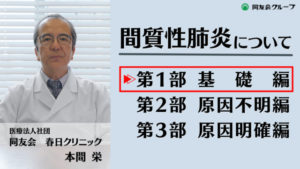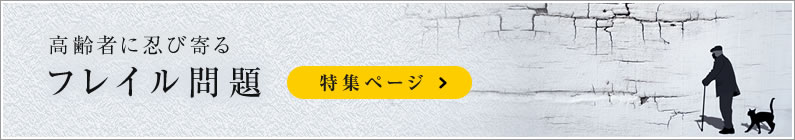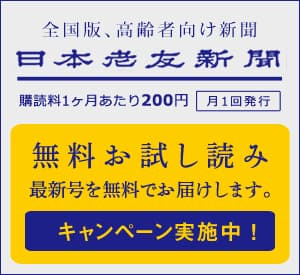コラム

マコのよもやま話 | 和泉 雅子
連載28 オッス!

日本舞踊のお稽古を始めた頃、TBSで、大ヒットドラマ『ありがとう』がスタートした。フー先生(石井ふく子先生)プロデュース、平岩弓枝先生脚本、チーター(水前寺清子さん)主演の婦人警察官の物語だ。もちろん私も、スリ係の婦警役。ドラマがスタートする前に、演出部から「合気道」を習ってください、とのこと。さっそく、警視庁の紹介で、新宿の「養神館」を訪ねた。
大きな玄関を入ると、壁一面に下駄箱があり、その先に広々とした道場が見える。「オッスッ」と突然大きな声。びっくりして尻もちをついてしまった。「あのう、和泉ですが」「あ、おまちしてました」早速道着をいただき、着替えて道場へ。
「合気道は、礼に始まり、礼に終わります」と担当の小川先生が言う。座っておじぎ。そして立つ。これをなんべんも繰り返した。いよいよ「かまえ」。両足を前後に開き、両手の指をパッと開いて、左手はおでこの前、右手はへそのあたり、手首をグッと前に出す。なんか、合気道の気分になってきた。腰を使い、すり足。相手のかかってくる力を利用して、投げる。なにやら日本舞踊のようで、楽しい。
さて、「受け身」の練習。仰向けにパタッと倒れて、両手で畳をたたき、頭をグッと持ち上げる。これが案外苦手だった。子供の頃から「でんぐり返し」が出来ない。跳び箱も2段でも跳べない。かけっこもビリ。からっきし、運動が苦手。小川先生にそれを言うと「じゃあ、でんぐり返し、やってみよう」「えー」やっぱり、いくらやっても出来ない。ついに、小川先生あきれる。
ある日、受け身の稽古をしていたら、頭を持ち上げるのを忘れて、畳に激突。目から、数知れない星が飛び出て、きれいだった。「和泉、大丈夫か!」「オオースウー」お弟子さん達が心配して、集まってきた。その時運良く星が消えたので、フラフラ立ち上がり、大声で「オッス!」全員で大笑いになった。この星事件がきっかけで、合気道が大好きになり、朝稽古に出て、日活の撮影所入り。帰りがけ夕稽古に出て、テレビ局入り。毎日、毎日、このパターンを繰り返した。
いよいよ『ありがとう』の収録が始まった。これだけ合気道の稽古をしたのだから、大丈夫。きっと見事に、犯人逮捕の場面もドンとこい!ところが毎週台本をいただくと、私だけそんな場面は、まったく、ない。下町のおせんべ屋さんで、姉妹二人暮し。姉役の藍子姉ちゃん(長山藍子さん)と、姉妹喧嘩の場面ばかり。ついに最終回まで逮捕劇なしで、6か月間の『ありがとう』の収録は、終わってしまった。
合気道に夢中な私、いよいよ初段の審査を受けることとなった。私より、小川先生の方がドキドキ。でも、いつもの稽古通り、おちついて出来た。晴れて初段。道場から、初段のお墨付きと、黒帯と、名入りの紺の袴と、木刀をいただいた。
養神館は、警察関係の方が多く稽古していたので、中野の警察学校から声がかかり、婦警さん達に「演武」つまり「かた」を十手ご披露することになった。うれしいことに、三年も続いた。
1986年、警察官募集のポスターに、85年の北極点遠征の写真が採用された。このころ、十代のアイドルがビルから飛び降り自殺したのをきっかけに、十代の子供達の飛び降り自殺が止まらなかった。そこで、このポスターを町中に貼ったところ、なんと、おさまった、と言う。お陰様で警視総監賞をいただいた。そして、憧れの110番のお部屋を見学。ベテランの婦警さんが近づいてきた。「中野で、演武を拝見したものです」「うわあ、うれしい。オッス!」「オッス!」と二人で握手して、もりあがってしまった。
思い起こせば、あの星いっぱい事件がなければ、今日の、この再会の、この感動はなかった。合気道をやって本当に良かった、としみじみ思った。
さあ、皆さま、ご唱和ねがいます。「オッス!」ありがとう。じゃあ、またね。
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。
- 和泉 雅子
- 女優 冒険家
- 1947年7月東京銀座に生まれる。10歳で劇団若草に入団。1961年、14歳で日活に入社。多くの映画に出演。1963年、浦山監督『非行少女』で15歳の不良少女を力演し、演技力を認められた。この映画は同年第3回モスクワ映画祭金賞を受賞し、審査委員のジャン・ギャバンに絶賛された。以後青春スターとして活躍した。
1970年代から活動の場をテレビと舞台に移し、多くのドラマに出演している。
1983年テレビドキュメンタリーの取材で南極に行き、1984年からは毎年2回以上北極の旅を続けている。1985年、5名の隊員と共に北極点を目指したが、北緯88度40分で断念。1989年再度北極点を目指し成功した。
余技として、絵画、写真、彫刻、刺繍、鼓(つづみ)、日本舞踊など多彩な趣味を持つ。 - 主な著書:『私だけの北極点』1985年講談社、『笑ってよ北極点』1989年文藝春秋、『ハロー・オーロラ!』1994年文藝春秋。
- 今注目の記事!