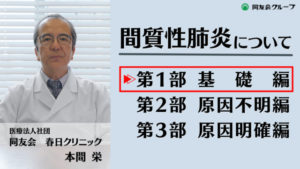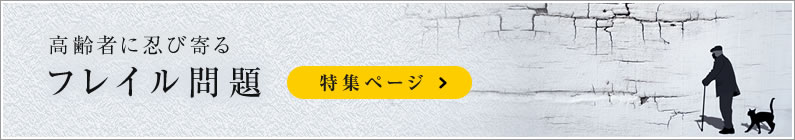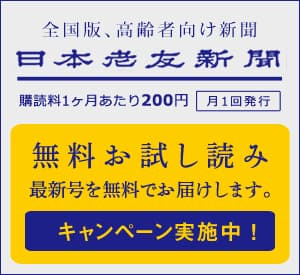コラム

マコのよもやま話 | 和泉 雅子
連載29 先輩すごーい!

TBSのドラマでは、なぜか職業を持つ娘役が多かった。日曜劇場では、娘チンドン屋、娘活弁士、炉端焼き屋、お好み焼屋。連続ドラマでは、上野道明の組み紐屋の娘。道明さんに教えていただき、本当に帯締めが組めるようになった。のちに、若山富三郎さんと舞台で共演し、「むしろ」を編む場で、演技ではなく、その手さばきに拍手喝采だった。
『娘すし屋繁盛記』では、母さんが森光子さん、父ちゃんが木村功さん。寿司コンクールで、女性初の優勝者になった娘さんが、モデル。昔、我が家は食堂で寿司もやっていたので、本番で握りたかった。近所の寿司屋にお願いして、毎日握った。握った寿司は料金を払って持ち帰ったので、家族はうんざりしていた。
『パリパリ娘奮闘記』では、表具店の娘。ふすま、障子張り、金屏風、書画の表装を生業にしている。やはり職人さんに習い、今でもふすまと障子張りは、できる。お父っつぁんは、中村翫右衛門(かんえもん)さん。この頃、歌舞伎の演目『ういろう売り』の口上に凝っていた。収録中、ライティングの直し待ちの間、お父っつぁんに『ういろう売り』をご披露!するとプロデューサーが慌てて駆け付け手招き。セットの隅に連れていかれた。
「あの方を、誰だと思ってるの」「うん、お父っつぁん。日活で『あゝひめゆりの塔』で共演してるよ」「あのね、歌舞伎出身で、前進座を立ち上げた名優さんで、日本の役者が尊敬している人なんだよ。その人に『ういろう売り』なんて、信じられない」うわあ、やっちゃったあ。でも、これがきっかけで前進座では若手の稽古に『ういろう売り』を取り入れたとか。エッヘン!
その後、舞台に誘われた。息子さんの『遠山の金さん』や『伝七捕物帳』でおなじみの中村梅之助さんの公演だ。孫は『信濃のコロンボ』や刑事物で人気の中村梅雀さん。さて、お父っつぁんから教わった、ありがたい話。「驚く演技をする時、小さな劇場で大きなヘビを登場させると、演技オーバーになってしまう。大劇場で小さな蛇を登場させると、驚いたように見えない。だから、劇場の大きさに合せて、ピッタリのヘビを登場させるんだよ」「うわあ、なっとく!」梅之助さん「きみはいいなあ。僕は、何にも教えてもらえないんだよ」とニッコリ笑った。
お父っつぁんの大ファンが、山田五十鈴先生。私が一人暮らしを始めた頃、山田先生と共演できた『女たちの忠臣蔵』だ。舞台裏でスタンバイしている時、毎日毎日、簡単な料理を山ほど教えてもらった。そして山田先生「女優だから、掃除、洗濯、炊事をしなくてもいいんだ、は、まちがいよ。家事がちゃんと出来ないと、良い演技は出来ないのよ。女優さんは、特別な職業ではないのよ。いろいろな職業のひとつなの。だから、ちゃんと家のことが出来るようになりましょうネ」ちげえねえ! 目が覚めた。大人になったような気がした。山田先生、すごーい!
これがきっかけで、山田先生主演のお芝居に、ほとんど誘っていただき、長いお付き合いになった。
私、五十四歳の時、芸術座で『夏しぐれ』が上演された。なんと、山田先生と京マチ子さんの競演で、私も呼んでいただけた。お二人の演技は、ただ、ただ、見応えがあり、目を皿のように見開いて、毎日、毎日拝見した。いまだに私の瞼に焼き付いている。
実は、山田先生と京さんと私は、それぞれ可愛がっているぬいぐるみがいて、毎日楽屋入り。山田先生の発案で、ぬいぐるみの記念写真を撮ることに。山田先生張り切っちゃって、小道具さんに頼んで、赤い毛氈(もうせん)と金屏風を設(しつら)え、カメラマンは、舞台のポスターを撮る大ベテラン。それぞれのぬいぐるみが正装で仲良く並び、記念写真は無事終了した。山田先生、記念にと、母にサマーセーターを。マークン(私のぬいぐるみ)には、カーキ色のポロシャツをプレゼントしてくれた。山田先生、すごーい。ありがとう。
じゃあ、またね。
老友新聞本紙1面に「マコのよもやま話」を連載いただいた和泉雅子様が7月9日に逝去されました。生前のご厚情に深く感謝するとともに、故人のご功績を偲び、謹んで御冥福をお祈りいたします。なお、本コラムに関しては生前に書き溜めていただいた原稿を引き続き掲載をさせていただきます。
老友新聞社
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。
- 和泉 雅子
- 女優 冒険家
- 1947年7月東京銀座に生まれる。10歳で劇団若草に入団。1961年、14歳で日活に入社。多くの映画に出演。1963年、浦山監督『非行少女』で15歳の不良少女を力演し、演技力を認められた。この映画は同年第3回モスクワ映画祭金賞を受賞し、審査委員のジャン・ギャバンに絶賛された。以後青春スターとして活躍した。
1970年代から活動の場をテレビと舞台に移し、多くのドラマに出演している。
1983年テレビドキュメンタリーの取材で南極に行き、1984年からは毎年2回以上北極の旅を続けている。1985年、5名の隊員と共に北極点を目指したが、北緯88度40分で断念。1989年再度北極点を目指し成功した。
余技として、絵画、写真、彫刻、刺繍、鼓(つづみ)、日本舞踊など多彩な趣味を持つ。 - 主な著書:『私だけの北極点』1985年講談社、『笑ってよ北極点』1989年文藝春秋、『ハロー・オーロラ!』1994年文藝春秋。
- 今注目の記事!