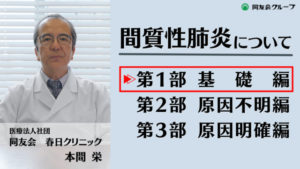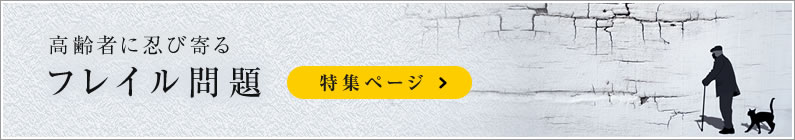コラム
極数「九」と菊〈重陽の節供〉

(本稿は老友新聞2019年9月号に掲載された当時のものです)
九月九日は重陽節供です。他の節供に比べてあまり知られていませんが、菊の節供とも呼ばれています。「重陽」の「重」は重なるという意味で、「陽」は本来「太陽」という意味があります。数では奇数を表わすので、重陽は陽数の極である九が重なった日です。
古代中国では、陰と陽は対立して、互いに消長を繰り返し、陽が極に達すると陰が崩し、陰が極に達すれば陽が崩すと考えられていました。
十は全数として数の頂点に立ち、満つれば欠けるという哲学上好ましくないとされ、「九」を、満ちて極まった数として、陽の極数、最高の数と考えて、天の数として神聖視されていたのです。また、九は「糾」「鳩」に通じ「あつまる」という意味を持ち、「完成させる」という考えももっています。
江戸時代、午前零時、午後零時(正午)を「九つ」といい、二時間を「いっとき」としていました。時を告げる鐘は、まず陽の極数である九から打ち始めて、この時刻を「九つ」と決め、次は九の二倍の一八鐘、さらにその次は九の三倍の二七鐘としたのですが、それでは多すぎるので二桁目を除いて、八つ打って「八つ」、七つ打って「七つ」と定め以下、六つ、五つ、四つを時刻としていました。
「九つ過ぎ」というと「ものの盛りを過ぎたこと」の意味からも九が頂点というのが解ります。
重陽と菊の結びつきは、酒に菊の花をひたして飲むと長生きが出来るといわれている「菊酒」と、菊に綿をかぶせて一晩置き、露にしめった綿で身体を拭くと長寿を保ち、邪気払いになる「菊のきせ綿」に由来しています。
キクという名は本来は日本語ではなく中国の菊の音によるものです。漢音で両手を丸めて水をすくうことを「掬」(キク)といい、「蹴鞠」のマリも「鞠」(キク)といいます。こうしたキクの語尾が変化してキュウ(球)になり、球状のものを人の手であれば手偏の「掬」、革で出来ていれば革偏の「鞠」という文字で表記し、球状の花を咲かせる草として草冠をつけたのが「菊」です。「菊」をキクというのは、植物の菊と一緒にその文字と呼び名が中国から伝わったといわれています。
菊の節供には菊合わせといい、香り高く気品があり、邪気をはらい寿命を延ばすとされる菊を鑑賞する行事が行われています。日本での菊見の宴は、天武天皇十四(六八六)年に行われたのが始まりとされています。また、栗を炊く習慣もあり「栗の節供」ともいわれ、「お九日」といって収穫祭の一環とする風習の地方もあります。
菊といえば十六葉八重表菊の皇室の御紋章ですが、これは、菊好きの後鳥羽上皇が定められたものです。また、大勲位菊花大綬章は最高の勲章とされ、旭日と菊花を合わしています。
夏の盛りがやっと過ぎても残暑厳しい頃ですが、菊の見頃はすぐそこまでやって来ています。浅草寺の菊供養会は十月十八日。この日に限り授与される「菊のお守り」には延命長寿の御利益があるそうです。
(本稿は老友新聞2019年9月号に掲載された当時のものです)
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。