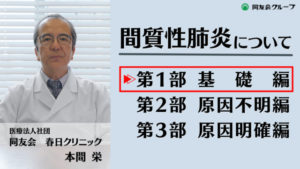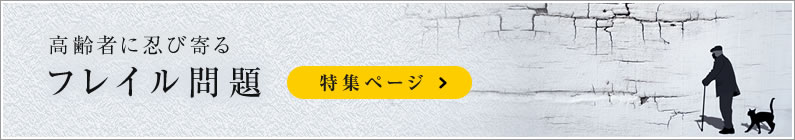コラム
行灯〈不便さの価値〉

(本稿は老友新聞本紙2019年10月号に掲載された当時のものです)
『徒然草』の百九一段に、「夜に入りて物の映えなし、といふ人いと口をし、万のものの綺羅、飾り、色ふしも、夜のみこそめでたけれ」というくだりがあります。夜は物が映えないという人がいるけれど、そんなことはなく、夜こそが美しい。夜の火影は素晴らしいし、香りも、ものの音も、夜のほうがずっと味わい深い。という意味です。
こんな感覚を実感することが出来たのは、時代劇に出でくる「行灯」を実際に体験したからです。
映像の世界では行灯に火を入れると、電気がついたように部屋全体がスッと明るくなりますが、あれはテレビや映画用につくられたもので、実際はとても暗い照明器具です。江戸時代の平均的な行灯は、百個以上も並べて60ワットの電球のやっと1個分の明るさだといわれています。しばらくして目が慣れてもやはり暗いです。
明るい照明に慣れている私は、昔の人はよくこの薄暗い中で夜の仕事が出来たかと思うのですが、当時は細かい仕事は裸火のもとで行っていたので、そのために、行灯の障子の一部が明けられるようになっているのです。確かに裸火に物を近づけると範囲は狭いものの、それなりには見えるのですが、やはり、ほおずき色の明かりは驚くほど暗いのです。
一晩中電気が消える事のない世界に慣れているので、昔の人はさぞ不便だったろうと思うのですが、それは今の私達のモノサシなので、それが当たり前の時代には不便さなど感じなかったのでしょう。行灯は確かに暗いのですが、真っ暗で何も出来ないということでもなく、裸火として使えばお裁縫も出来るし、読書だって昔は今のように細かい活字ではないので楽しめたのです。
だからといって、夜と昼が逆転するほどの明るさからは程遠いので、人は自然と早寝をし、大部分人は夜明けと共に起きて日が暮れればなるべく早く寝るという、生物的には当然な生活を送っていたのです。
実際に行灯を裸火にして着物の襟つけをしてみたところ、狭い範囲しか見えないために何も考えずチクチクと、以外に集中し落ち着いてはかどりました。次に浮世絵を行灯のもとで見ると、絵の奥行や絵師の個性がひとつひとつ際立って浮かび上がってくるのです。
微妙ではありますが移ろいゆく筆使いなど行灯の光は教えてくれました。
今回、行灯を体験することにより、不便さの価値を粗末にし、便利さの価値を重視することで文明に追い立てられている生活だとつくづく感じました。今の生活を変える事など不可能ですが、体験した事による気づきは計り知れなく大きなものでした。
行灯まで使用しなくても、もっと簡単に「和ろうそく」はいかがでしょうか。電灯とは違うとろりと揺らぐ柔らかな火のもとで、絵画や写真を眺めると今までは見え方が違って新しい発見もあるはずです。
なんとも心が落ち着き夜の長いこれからの季節はゆったりとした気持ちで過ごせると思います。くれぐれも火の用心は忘れずに。
(本稿は老友新聞本紙2019年10月号に掲載された当時のものです)
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。