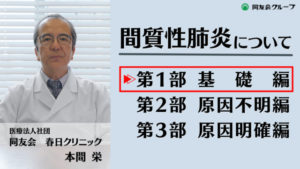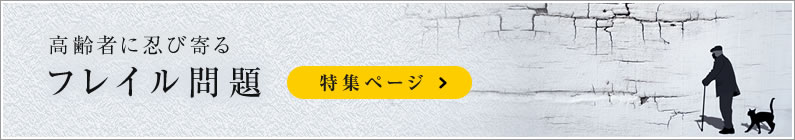コラム
第16回 壮大な大阪城の歴史

大阪城は城内の古い建造物13楝が重要文化財に指定された国の特別史跡です。その歴史は中世の石山本願寺、豊臣秀吉が築城した豊臣大阪城、徳川幕府により再建された徳川大阪城と三つの時代に築かれた城郭からなっています。その壮大な石垣や縄張りは他には類を見ない規模。今も人々を魅了するその歴史を辿ってみます。
3つの時代に築かれた城郭

大阪の別名と言われる石山の地は、信長が最終の居城と考えていたという一説があります。大阪城といえば秀吉をイメージしますが、信長が11年の歳月をかけて攻め続けた浄土真宗の石山本願寺があった場所で、一向宗の本拠地でもあり濠や土居などの防護機能を持ち鉄砲集団の雑賀衆とも通じ、多くの僧兵を抱え信長と敵対しましたが、その後朝廷の介入により和議が結ばれ本願寺は紀州に移されます。その時、放火ともいわれた火事で全山が焼失してしまいます。
本能寺の変後、信長の後継者となった秀吉は本願寺の遺構を利用して難攻不落の名城、大阪城を築城します。西国30あまりの大名に命じた築城で、本丸の造築の動員数は23万人を越えたといわれ、その経済力、労働力からほぼ2年の歳月で金箔瓦の5層8階の大天守、千畳敷の御殿が並ぶ郭と城下町を囲む総構えを持つ壮大な城が完成しますが、大阪夏の陣で徳川に攻められ落城します。
その後、徳川幕府二代将軍秀忠は西国有事の備えとして幕府の軍事拠点として、西国64藩に命じ大阪城を再築城します。現在の大阪城はこの時築城された13楝が重要文化財として残っており、石垣や各曲輪は他に類を見ない壮大なスケールです。鉄骨鉄筋コンクリート造りの天守が復興されたのは昭和6年ですからかつての天守より長い歴史を刻んでいます。
大阪城周辺の整備や「平成の大改修」を経て、美しく生まれ変わった天守閣に加え、音楽ホール、スポーツ施設が備わった日本でも指折りの文化施設と公園になっている、大阪城は大阪市発展に伴った市民の誇りです。
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。
- 今注目の記事!